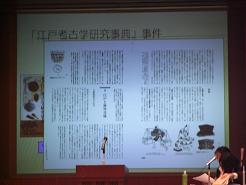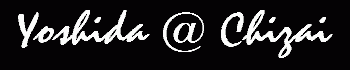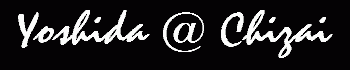
seminar > 2008交流戦 紹介・ルール説明
目次
紹介・ルール説明
プログラム
- 1 挨拶
- 2 選手入場
- 3 校歌斉唱
- 4 メンバー紹介
- 5 事案紹介
- 6 ルール説明
- 7 ディベート
- 8 ジャッジ
ルール説明
- 1 進行
- (1)立論
- (2)第一尋問
- (3)第二尋問
- (4)最終弁論
- ・各チームは、あらかじめ立論1名、尋問2名、最終弁論1名のフォーメーションを決定する。
- ・尋問は2名のうちそれぞれが1回ずつ行なう。回答する側は4名全員が答える。
- ・それぞれの間に1分間の作戦タイムをおく(ただし、最終弁論の前の作戦タイムは3分間とする。
Xの最終弁論とYの最終弁論との間は作戦タイムなしとする。)
- 2 ルール
- ・両チームは、それぞれ当該ケースにおける原告(X)または被告(Y)の代理人弁護士となって主張を展開する。
- ・原告X側は、原則として、現実のケースにおいて原告側が主張した請求の全部または一部を、自由に決定した論拠(理由付け)に基づき主張するものとする。
- ・ディベーターの主張は原則として口頭により行なう。したがって、ジャッジに対して独自にレジュメを配布するといったことは原則としてできない。
ただし、係争物件や他例を示す等の目的で物(図表、関係図など)を刑事・呈示等することは認められる。
その他、資料の配布については、相手チームの承諾があれば許されるものとする。
- ・最終弁論は、この時点までの議論を総括して行なうものであるから、ここで新たな論点や理由付けを持ち出すことは認められない。
- 3 ジャッジ
- ・ジャッジは判定基準に従い、判定用紙にコメント及び判定結果を記入する(5分間)。判定結果は、いずれかの優勢またはドローと定める。
- ・勝敗は、両校から10名ずつ選抜された代表ジャッジ(計20名)により決するものとする。同数の場合はドローとする。