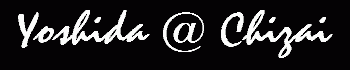目次
1. 概要
吉田ゼミでは2012年度後期は1チーム3人のディベート形式でゼミを行っております。
1.1 進行
ゼミは以下のように進められます。
| 事前説明 | ||
|---|---|---|
| ディベーター自己紹介 | 3分程度 | |
| 事件の概要説明 | 10分〜20分程度 | ディベート |
| X立論 | 8分以内 | |
| インターバル | 1分 | |
| Y立論 | 8分以内 | |
| インターバル | 1分 | |
| X尋問 | 6分以内 | |
| インターバル | 1分 | |
| Y尋問 | 6分以内 | |
| インターバル | 2分 | |
| X再尋問 | 6分以内 | |
| インターバル | 1分 | |
| Y再尋問 | 6分以内 | |
| インターバル | 1分 | |
| X最終弁論 | 5分以内 | |
| Y最終弁論 | 5分以内 | 判定 |
| ジャッジペーパー記入 | 10分 | |
| 休憩 | 10分程度 | |
| ジャッジコメント発表 | 20〜30分程度 | 講評 |
| 吉田による講評 | 10分程度? | |
| 質疑応答 | 10分程度? |
1.2 ルール
ジャッジにあたり気をつけるべきルールは以下のようになっております。
- ジャッジの対象となるのはディベート中のディベーターの振舞い全て。
- ジャッジ同士は相談してはならない。質問もできない。メモをとることはできる。
- 判定の対象はどちらのディベーターの主張内容・方法が勝っているかであって、 ジャッジ自身の見解がどちらであるかということではない。また、判例の動向や学説の勢力状況がどちらに味方しているかで勝敗を決めてはいけない。
ジャッジする際の判断材料の一例として、以下の点があります。
- ディベーターの態度 (マナーは守られているか)
- 法律構成が難解すぎないか (論旨はわかりやすいか)
- 尋問に対し適切に答えていたか
- 争点に関して十分な反論がなされたか
- 論理は一貫しているか
2. 実際の様子
2.1 事件紹介

16:30に当日のディベーターの自己紹介があり、その後、吉田から事件の概要説明があります。 ここでは、その日のディベートのモデルケースの当事者関係、そのケースで問題となった法律的な事柄、事件の当時についての一般的な情報など、 ジャッジをするために知っておくべきことが説明されます。
2.2 ディベート




20分程度の説明の後、ディベートに移ります。
まず原告X側の立論があり、その後被告Y側の立論、X尋問、Y尋問、X再尋問、Y再尋問、X最終弁論、Y最終弁論と進みます。 なお、各パートの間には1分間のインターバルがあり、その間にディベーターは話し合うことができます。
ジャッジはこの間ディベーターの主張の内容や振る舞いなどについてメモを取ることができますが、ジャッジ間で事件についての相談は一切禁止となっています。
立論でディベーターはモデルとなった事件に沿う形で互いに主張を行い、自説を事実に基づいて論理付けて説明します。 X立論ではYへの請求の内容、請求の理由が述べられます。 Y立論は、まずX主張の認否を述べ争点を明らかにした後、X主張の争点部分についての反論や抗弁が述べられます。
尋問・再尋問では、ディベーターは相手への質問を通して、 相手方の主張・争点を明らかにし、相手の主張の不備を指摘、自己に有利な情報を相手の口から引き出していきます。
最終弁論では、ディベーターは尋問の内容を踏まえて自己の主張の正当性、相手の主張の失当性をジャッジに説明します。 双方、これまでに述べられた内容をわかりやすくまとめた説明となります。
2.3 判定



ディベートが終わると10分間のジャッジペーパー記入時間と10分程度の休憩時間があります。 休憩終了後にジャッジは一人ずつジャッジの結果とコメントを1分程度で発表します。
ジャッジは、判決のように自分が妥当と思う結論、自身の価値判断から原告被告の勝敗を決めるのでなく、 ディベートにおいて自分がどちらのディベーターを支持するかで勝敗をつけます。 ジャッジはディベート中のディベーターの態度や主張する論理の一貫性、論旨のわかりやすさを材料にして、 どちらのディベーターがディベート上勝利しているかを判断することになります。
ジャッジ全員の勝敗発表とコメントの終了が終われば、結果が発表されます。
2.4 講評

最後に吉田から戦略についてのコメントなどディベート全般に対しての講評があります。 この時、吉田の判定も発表されますが、これはディベートの勝敗には関係ありません。
また、ゼミに参加していて質問があれば、講評の最後に質疑応答の時間がありますので、ここで質問することができます。
3. オープンゼミについて
法学部 吉田広志ゼミでは、11月28日以降のゼミのジャッジ参加者を募集しております。 ジャッジは学年、学部生/院生問わず、席がある限りどなたでも参加できます。 オープンゼミの参加にあたり、連絡・知的財産法の知識・予習は特に必要ありません。 事案についての説明がございますし、ディベーターの説明はわかりやすさを重視したものとなっております。 来年度のゼミ選択の参考に、学部2年生の積極的参加をお待ちいたしております。
なお、学部2年生は見学のみの参加も可能となっております。
実施日と事件名
- 12/18 match 9 [ギャロップ・レーサー]
- 1/10 match 10 [正露丸]
- 1/15 match 11 [TVアタック]
- 1/22 match12 [キャンディ・キャンディ]
事件の詳細については2012年度後期ゼミ事件リストよりご覧ください。
場所
W101 (W棟1階、法学部方面の教室です。)
謝辞
このディベートの実施にあたっては、立教大学上野達弘助教授にご指導とご助力いただきました。 この場を借りて厚く御礼申し上げます。